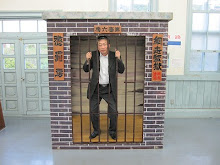秋深しの今日この頃です。いろいろなことに季節を感じますが、シャワーがお湯になるのにだいぶ時間がかかるようになって、秋を実感しています。
電車で3人がけの端に座っていて、真ん中が30代後半のお兄さん、反対の端が60台の重役風のおじさん。お兄さんが携帯を取り出してメールを見ようとしたら、おじさんが大声で、「電車の中で携帯を使っちゃいかん!!」
お兄さん「電話してませんよぉ、メール見ているだけじゃないですか?」
おじさん「ここは優先席だ、携帯は電源を切ろと書いてある!」
お兄さんしぶしぶ電源を切る。
おじさんは返す刀で向かいの別のお兄さんに、「そっちも、電源を切りなさい!!」
車内はシーンと静まり返りました。
この前、携帯の電源が入っているために飛行機が飛べないということがありましたね。自分は飛行機でもあまり電源を切らなかったので、少し反省、電源は切りましょう。でも、電車の中で、電源を律儀に切っている人を見かけませんね。
そもそも、1980年代にPHSが一般化したときに、その電波で、点滴ポンプや植込式ペースメーカーが誤作動することが、電源を切りましょうの初めです(実際母の病室でPHSを使うたびに点滴が止まった経験があります)。今は、ペースメーカーはまず誤作動しません。胸のポケットに入れておいても、大丈夫だと思います。でも、そのときの名残というか過剰反応でしょうね。
おじさんの言っていることは正論です。だから誰も反論できないのですが、でも誰も守っていないルールで公衆の面前で怒鳴られたお兄さんもかわいそうです。
法律には遵守率というのがあるそうです。皆がどれだけ守っているかということですね。「人を殺してはいけない」は遵守率は限りなく100%に近いですが、それでも殺人事件が起きるので100%ではないですね。本来、法律とかマナーとかは遵守率100%を目指し、法律の場合は違反者の検挙率も100%を目指すべきですが、「水清くして魚棲まず」というのが世の常、大体がいい加減です。
遵守率の低い法律を「ザル法」といいますが、どんなものが思いつくでしょうか?定義は、法律で禁止されているにもかかわらず、遵守率が低く取り締まりも形骸化している法律です。
・道路交通法:スピード違反が常態化、逆に遵守したら交通渋滞で皆困るでしょう。
・建築基準法;大阪では半分の建物が建築基準法違反らしい。
・賭博罪:マージャン屋やパチンコ屋では賭けが常態化、そもそも合法とはいえ最近のサッカーくじや宝くじは射幸性が異常に高いです。政府は国民に冷静な確率計算を教育すべきです。
・労働基準法:サービス残業が常態化、とくに医療者は聖職という美名の下に残業代が出ませんね。
・鉄道営業法:定員超過の乗車が当たり前、マナー以前です。などがあります。
医師法第19条は「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」というのがありますが、これも100%遵守するのは難しいようです。
写真は近所の庭の秋です。