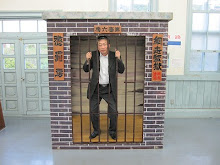今日は神田のすし屋と居酒屋で終電まで。終電は鷺沼どまりでそこから深夜バス。家に着いたらもちろん午前様。
この自堕落を反省し、皆さんと世の中の名言を鑑賞しましょう。 長いですがついてきてください。
○御互(おたがい)に忙がしい切りつめた世の中に生きているのだから
御互に譲り合わなくては不可(いけ)ない。
― 夏目 漱石 ― (『書簡』)
▼漱石先生の時代も忙しい切り詰めた時代だったのですね。現代を見たらなんとおっしゃることやら・・・
加齢についての名言を少し集めてみました。
○この世は無常迅速というてある。
その無常の感じは若くてもわかるが、
迅速の感じは老年にならぬとわからぬらしい。
― 倉田 百三 ― (『出家とその弟子』)
▼最近とみに月日の経つのが速いと感じます。それは記憶力の低下が原因という説があります。一年前のことどころか昨日のことも覚えていない(ーー;)
○私は「四十にして惑わず」という言葉の裏に
四十は惑いやすい年齢であるという隠れた意味を認めたい。
― 寺田 寅彦 ― (『厄年とetc.』)
▼ということは、五十にして天命を知るという言葉の裏には、五十では天命を知りにくいという隠れた意味がありますね。
○若いとか年とっているとかいうことは、
凡庸な人たちの間にだけあることだ。
あるときは年をとり、あるときは若くなるもの。
ちょうど、うれしいときがあったり悲しいときがあったりするように。
― ヘルマン・ヘッセ ― (ドイツ作家)
▼これは中年、初老の励みになります
○年を重ねただけで人は老いない。
理想を失う時に初めて老いがくる。
― サミュエル・ウルマン ― (『青春』)
○ネコが年をとると、だんだん図々しく無気味になってくる。
女もうっかり年をとると、似た性格を帯びてくる。
― 平林 たい子 ― (『にくまれ問答』)
▼これは平林さんが言った言葉で、僕の言葉ではありません。そこのところ間違えないように。
○昔は年寄りになって、何も出けんようになると、もっこに入れて山へふて(棄て)に行く時代があったんと。
― 岩波文庫 ― (『日本昔話』)
▼日本昔話には、後期高齢者保険を予知した部分があるようです。より高齢化が進むと、末期高齢者保険制度を作るのでしょうか?
加齢から離れましょう。
○読書もとよりはなはだ必要である、
ただ一を読んで十を疑い百を考うる事が必要である。
― 寺田 寅彦 ― (『知と疑い』)
▼科学者には大事なことと思います。Critical thinkingと英語では言うようです。
○綺麗な靴を穿(は)いていた者は心してぬかるみをよける。
だが一旦靴が泥にそまると、だんだん泥濘(ぬかるみ)を恐れなくなる。
― 長与 善郎 ― (『青銅の基督』)
▼朱に交われば赤くなるといいたいのでしょうか?それとも石の上にも3年的なことを言いたいのでしょうか?
○薔薇に対するヨーロッパ人の讃美を、
我々は分つことをえない。
薔薇は桜の単純さを欠いている。
― 新渡戸 稲造 ― (『武士道』)
▼分かつことをえないとは、わからないという意味ですね。季節的名言です。春のこの時期、「薔薇は桜の単純さを欠いている」と言いたいですね。漢字の話ではありません。
○秘すれば花なり、秘せずば花なるべからず。
― 世阿弥 ― (『風姿花伝』)
▼薔薇・桜→花の連想です。最近、モロダシが多くてヘキヘキします。
○世界を怖るるな。ただ自己を怖れよ。
四面楚歌の声のなかにあっても、屈せざるがこれ男子の本懐である。
自ら信じて行なえば、天下一人といえども強い。
正義が常に念頭にあるからである。
― 杉浦 重剛 ― (教育者)
▼誰かご存じないでしょうね。明治時代の国粋的教育者です。一校の校長も勤めました。自分はプチ国粋なのか「男子の本懐」といわれると背筋が伸びますね。
○愛するということは、
愛されないかもしれない覚悟も含めた上に、
成立する感覚なのよ。
― 落合 恵子 ― (『自分にごほうび』)
▼当たり前のことでも、レモンちゃんが語りかけると納得したりして・・・
○明日を耐え抜くために必要なものだけ残して、
あらゆる過去を締め出せ。
― ウィリアム・オスラー ― (イギリス医学者)
▼医学教育の神様みたいな人です。そんな人に掃除をしなさいといわれているみたいです。「捨てる技術」をまた読みましょう。
感想をお待ちしています。よろしくお願いします。