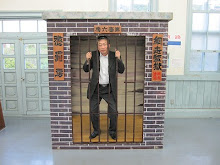午前中はアフガニスタンからの研修生にOSCE(客観的臨床技能試験)についての講義。
昼休みは、湘南鎌倉病院の大リーガー医師(北米の総合臨床指導医の総称)の講演の司会、夕方は、東京都臨床検査技師会血液班の講演会で、コミュニケーションのお話をする。パワーポイントを使って講演するのですが、その準備がもう泥縄状態です。
泥縄とはもちろん「泥棒を捕らえて縄を綯う」の略ですが、もう泥縄とちゃんと変換されます。広辞苑でも泥縄でのっています。それに、今の若い人は縄を知らないでしょうし、綯うという動作を知らないでしょうね。両足の親指にわらを挟んで縄を作る姿や、縄を作る機械など見たこともないでしょう。現代風に言うと「泥棒を捕らえてビニール紐を買いに走る」ということになるでしょうか?あるいは「泥棒を捕らえてセコムに入る」ということでしょうか?
ことわざの短縮形が一般化したのには、棚ぼたというのがありますね。棚から牡丹餅の略ですが、広辞苑にも棚ぼたで載っています。
このことわざのイメージは、神棚の下あたりで口をあけて寝ていたら、何かの拍子に神棚に備えてあった牡丹餅が落ちてきて口の中に入るというものなのですが正解でしょうか?
この場合、なぜ牡丹餅が落ちてきたのでしょうね。それから、仏壇にはお供えをするのですが、わが家ではあまり神棚にお供えはしなかったような記憶があります。
別の解釈は、ただいまぁーと外から帰ってきて、戸棚を空けるとおやつに牡丹餅があったというのですが、あまり幸運に恵まれたという感じが出ませんね。
ほかにことわざの短縮形が一般化したというのはありますかねぇ?犬棒とは言いませんよね。猿木とも言いませんね。河童川とも、猫手とも、濡れ泡とも、豚真とも言いませんね。何かほかにもありそうな気がするのですが思い出せません。
こんなことを考えているから、仕事が片付かないのですね。
skip to main |
skip to sidebar
日々のことをつれづれにつづりたいと思います。 写真も多く使いましょう。 青春という曲より、青春Part2という曲のほうが好きです。 感想をぜひ筆者にメールでお送りください。 書き込むと混乱するかもしれないし、そもそも面倒です。