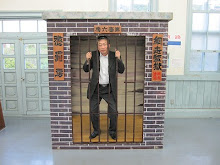今日は、午前中から会議で、午後は自治医科大学看護学部での講義、今日のテーマは、医療安全。結構楽しい授業でした。パワーポイントを紹介したいです。
実は、時間を間違えて早く着きすぎたので、自治医科大学病院地下で床屋さんに行きました。下手ではないものの、9月の尼崎の名人には及ばないですね。
夕方は、神田学士会館で、3代前の小児科名誉教授の傘寿の会。大勢の人が集まっていました。挨拶で、今までのご活躍の紹介や、ご指導への感謝は当然として、これからもますますご活躍くださいというのはかわいそうな気もしました。
それが終わって、大学に戻ってきたら秘書さんがいました。
「傘寿は80歳のお祝いですね。なぜだか知っていますか?」
「かさですか?分かりません。」
「傘を略字で書くと八十と書くからですよ。それでは、卒寿というのは何歳か知っていますか?」
「卒業の卒ですか?」
「これも略字で書くと九十と書くからですね。米寿は?」
「88歳ですよね。米を分解すると八十八になるからでしょう。」
「良く知っていますね。」
「この前先生から習いました。忘れたんですか?」
「白寿は?」
「分かりません。」
「99歳です。」
「どう分解しても九十九にはなりませんが・・・」
「これは、とんちで、百から一をひいて、白になって九十九歳です。」
「それなら日寿は98歳で、口寿は97歳ですか?」
「そなことはいわないです。喜寿は何歳ですか?」
「わかりません」
「77歳です。喜という字を草書体で書くと七十七に似ています。」
「先生良く知っていますね。草書体で書いてみてください。」
「書けません。古希は何歳ですか。」
「70歳ですか?」
「良く知っていますね。」
「勘です」
「論語に、吾十有五にして学に志すから始まって、 三十にして立つ、四十にして惑はず、五十にして天命を知る、六十にして耳順ふときて、七十にして心の欲する所に従いて、 矩(のり)を踰(こ)えずとあります。」
「すごいですね、先生論語を良く知っていますね。そのあとに、70歳は古希というとあるのですか?」
「ごめん、古希は、論語ではなかったみたいです・・・(註1)。還暦というのは何歳か知っていますか?」
「赤いちゃんちゃんこを着るやつですよね。なぜ60歳を還暦というのですか?」
「子丑寅・・・というのは知っていますよね。十二支ですよね。それ以外に、甲乙丙丁・・というのがあってこれが十個あります。」
「甲が優、乙が良、丙が可で丁が不可というのですよね。その続きもあるのですか?」
「十個あるのですが、僕もいえません(*^_^*)(註2) それに成績の順ではなくむしろ方角を表していたのではないでしょうか?日本語の読み方もあり、甲をきのえなどと読みますよね。ひのえうまなどといいますね。」
「先生、漢字で書けるのですか?」
「漢字では書けません。ひのえうまに生まれた女は、男を食うということで嫌われますよね。だから、いつも丙午のときは、子供が少ないですね。」
「何で、女だけでなく、男も少ないのですか?食べられたのでしょうか?」
「これは迷信で、ほんとうに食べられるわけはありません。そいで、十二支と、十干の最小公倍数というのは分かりますか?」
「先生、私、文科系なんですけど・・」
「2と3の最小公倍数というのは、どちらの数でも割り切れる一番小さな数ですね。だから6。12と10の最小公倍数というのは60になりますね。だから、60歳を還暦といいます。」
「その、暦が回るというのがよくわからないのですが・・暦が回って戻ってくるというあたりがわかりにくいです。」
これから先、泥沼の解説が続きました。赤ちゃんに戻るから赤いちゃんちゃんこを着るあたりまで理解してもらえたでしょうか?
註1 古希は70歳のこと。唐の詩人杜甫の曲江詩「人生七十古来稀」に由来するという。論語ではありません。
註2 甲(こう)乙(おつ)丙(へい)丁(てい)戊(ぼ)己(き)庚(こう)辛(しん)壬(じん)癸(き)ちなみに別の読み方だと甲(きのえ)、乙(きのと)、丙(ひのえ)、丁(ひのと)、戊(つちのえ)、己(つちのと)、庚(かのえ)、辛(かのと)、壬(みずのえ)、癸(みずのと)
skip to main |
skip to sidebar
日々のことをつれづれにつづりたいと思います。 写真も多く使いましょう。 青春という曲より、青春Part2という曲のほうが好きです。 感想をぜひ筆者にメールでお送りください。 書き込むと混乱するかもしれないし、そもそも面倒です。